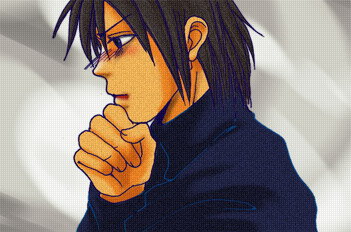moonrise
「どうだ、怪我の具合は?」
深夜、里へ通じる大門の前に、二人の人影があった。そのシルエットから察するに、一方は女性だろう。
動物を模した面を被った二人――おそらくは暗部。
「大したことはありません。あなたに治療していただきましたし」
「だが、一応病院へ行ってちゃんと治療してもらえ。わたしはこれから火影さまに報告してくる」
黒い猫の面を被った人物は、その声音から女性と判断できた。もう一方の鳥面が否やと首を振る。
「あなたの方こそ、傷を負っているではありませんか!」
「これくらいなら大丈夫だ」
言葉とは裏腹に、その指先からは血の雫がポタリポタリと滴り落ちていた。
「さっさと行け。リーダーはわたしだ」
「ですが・・・っ!」
鳥面も引き下がらない。埒があかぬと思ったのか、猫面は小さくため息をついた。
「わかった・・・。報告が終わったら、わたしも病院に行く。だから、先に行け」
「わかりました。必ず、ですよ?」
「くどい」
「すみません。では、先に行っています」
渋々と言った風情の鳥面を見送り、猫面は深夜の火影邸へと向かった。
「おそーいっ、ってば!一緒に昼メシ食おうって約束してたのにー」
「ごめん、カカシ!ちょっと寝坊しちゃった」
遅刻はカカシの専売特許なのにねぇ、とは笑った。
「昨夜、任務だったのか?」
「うん、まぁね」
ここは人生色々――デスクワークをこなすカカシの前にはちょこんと腰掛けた。
「ちょっと戻ってくるのが遅くなっちゃって」
「そうか・・・。ケガはしてないのか?」
「相変わらず心配性ね、カカシお兄ちゃんは」
クスクスとが笑う。
「心配にもなるデショ」
二人は家が隣同士で、幼馴染だった。そして、共に木の葉の里の忍であった。
「報告書は?」
「ああ、もう昨夜報告してきたし」
提出してきた、とは言わない。報告書の要らない任務――それはおそらく暗部としての任務。
カカシは一瞬をじっと見つめ、そうか、とだけ答えた。
「あまり心配させるな」
「うん、ありがと」
お茶を飲みながら、他愛もない話をする。すると、ふと人影が二人の傍に立った。
「さん?ゴホゴホ」

そこには、顔色の悪い青年が立っていた。特別上忍の月光ハヤテである。
いかにも不健康そうな雰囲気をかもしだしているが、彼もまた優秀な木の葉の忍のひとりである。
「あ、ハヤテ!怪我の具合はどう?」
「――その言葉、そのままそっくりお返ししますよ」
「え?」
「昨夜、『必ず病院に行く』と私と約束しましたよね?」
「えー?そうだったっけ?(すっとぼけ)」
「・・・さんっ!」
「もー、何そんなに怒ってんのよ、ハヤテってば。大したことないって言ったでしょ」
「――イヤなんです」
「は?」
「あなたの綺麗な身体に傷がつくのがイヤなんです」
「もう傷だらけだよ?」
だって忍者だし、とケラケラ笑うの腕を捕まえたハヤテは、そのままズルズルと引っ張って病院へ連れて行こうとする。
「っ!オマエ、やっぱりケガしてたのか!」
微かに血の匂いを感じ取っていたカカシだったが、それは昨夜の任務の名残だと思っていた。
だから、あえて深く追求しなかったのだ。
「大したことないってば」
むぅとはくちびるを尖らせたが、カカシもハヤテも引き下がらない。
「オマエねぇ、いくら病院嫌いだからって・・・。ハヤテ?」
「はい」
「悪いけど、コイツを病院へ連れて行ってやってくれ。途中で逃がすなよ」
「ちょっとぉー!大丈夫だって言ってるのに」
逃げ出そうとしたの気配を察知したのか、カカシに捕捉される。
「やーだーっ!病院キライー!!」
ジタバタとは暴れるが、カカシとハヤテ、二人が相手では敵うわけもなく。
「オイ、テメエら何騒いでんだ?」
「あ!アスマ!!いいとこに来たー!二人があたしのことイジメるんだよ!」
が二人の腕の間をすりぬけて、その背に隠れたのは、上忍の猿飛アスマだった。
いつものように紫煙をくゆらせながら、ゆったりと立っている。
「人聞きの悪いコト言うんじゃないよ、」
「そうですよ、さん!ゴホゴホ」
「イーッだ!」
強い味方が現れたと思ったのか、はアスマを盾に反撃にでた。
「アスマ、助けて!」
「おい、アスマ!を捕まえてくれ」
「んぁ?、なんかやったのか?」
油断していたのか、はあっさりアスマに首根っこをつかまれ、捕まえられてしまった。
「離してよー!」
「いい加減あきらめて、一緒に病院へ行ってください。ゴホ」
今度こそ、ハヤテとカカシに捕まり、は逃げられなくなっていた。カカシから事情を聞いたのだろう、アスマも
「ちゃんと病院へ行っとけ」
とに言った。ぷぅとふくれっ面のの頭をポンポンと叩く。
「ちゃんと病院へ行ってきたら、後でなんかうまいモンでも奢ってやるよ。今晩、飲みにいくか」
「・・・わかった。デザートもつけてよね」
渋々承知したは、ハヤテに引きずられるようにして病院へ向かった。
そして、一部始終を見ていた紅とアンコが深いため息をついた。
「の病院嫌いにも困ったものね」
「ほ〜んと!それにしてもさぁ、アンタたち、に甘いわねーっ」
ウンウンと、隣で紅も頷いている。
「カカシさぁ、アンタ、の育て方間違ったんじゃないの?」
「別にオレが育てたワケじゃないデショ」
「任務になったら別人みたいに切れ者だけど、どーして普段はああ鈍いのかしら?」
「ああ、ハヤテのこと?」
「そーよ!あの『あなたの綺麗な身体に傷がつくのがイヤなんです』って、超意味深じゃん!」
紅とアンコはものすごーく楽しそうである。ヒトの色恋ほど楽しいモノはないのだ。
「ねぇ、カカシ?」
「んー?」
「ちゃんと捕まえておかなきゃ、ハヤテに持っていかれちゃうわよ?」
「は妹みたいなモンで、そーゆーんじゃないよ。何回言えばわかるの」
カカシの表情は、額宛と口布で読めない。紅は小さくため息をついた。
「ねーねー、今晩飲みに行くんでしょ!一緒に行ってもいい?」
「オマエにゃ奢らねぇぞ、アンコ」
「わかってるわよ」
あの様子では、にくっついてハヤテもやってくるだろう。もちろん、アスマもカカシも。
こんな面白いものを見逃す手はない、とアンコは楽しげな笑みを浮かべた。
はムスッとした表情のまま、ハヤテの2歩ほど先を歩いていた。
「怒ってるんですか?・・・ゴホ」
「べっつにぃ」
――怒ってるじゃないですか。
ハヤテは小さくため息をついた。
「あなたのことが心配なんです」
「だーかーらー、大丈夫って言ってるでしょ?」
「どうしてそう病院ギライなんです?ちゃんと治療してもらえば、その腕の痛みをガマンしなくても・・・」
が足を止めた。
「病院はキライなんだもん・・・」
「・・・・さん」
珍しく頑ななに、ハヤテはなんと言っていいのかわからなかった。
その沈黙を破ったのは、顔なじみの特別上忍の声だった。
「お、じゃん」
「ゲンマ・・・?久しぶり」
そこに現れたのは、不知火ゲンマだった。
「ん?なにシケた面してんだよ」
ゲンマが、の頬をむにとつねった。
「いでで。何すんのよ?」
むぅとふくれた。ゲンマはニヤリと笑った。
「オマエにゃ、そんな暗い顔は似合わねぇよ。大口開けて笑ってるほうが、オマエらしいぜ」
「それって、褒めてんの?けなしてんの?」
「ああ?褒めてんに決まってんだろ。惚れたオンナにゃ笑っててほしいだろーが、オトコとしてはよ」
「もぉ〜。相変わらず口がうまいんだから」
「本気だって言ってんだろ?」
クスクス笑うを見つめるゲンマの瞳はとてつもなく優しい、とハヤテは思った。
思わぬ伏兵登場ですね・・・。
完全に無視された状態のハヤテとしては面白くなく、二人の間に割って入った。
「さん、そろそろ行きましょう。ゴホゴホ」
「・・・へーい。わかった、わかった。んじゃ、ゲンマ、あたしそろそろ行くわ」
「なんだ、ハヤテと任務なのか?」
チラリとこちらを見たゲンマの瞳は冷たい。まるで恋敵でも見つけたような・・・。
「ちょっとヤボ用」
「そっか。今晩ヒマなら、飲みにでも行かねぇか?」
「行く行くッ!・・・って、アスマに奢ってもらう約束したんだった」
ゴメン、と言いかけたを制し、ゲンマは言葉を続けた。
「別に俺も行ってもかまわねぇだろ?」
「あ、うん。人数多い方が楽しいしv」
ほんじゃね、とヒラヒラ手を振ってゲンマと別れる。
ゲンマのキツい視線が背中に突き刺さるようだ、とハヤテは思った。
ゲンマと別れてようやく病院へ歩き出したに、ハヤテはホッとしていた。
だが、しかし・・・。
「あ!」
ハヤテが『え?』と思った瞬間には、の姿は数十メートル先にあり、しかも誰かに抱きついていた・・・!
「イルカちゃん、見っけーっ!」
「うわぁぁ!?」
イキナリ背後からに抱きつかれ、情けない(?)悲鳴をあげたのは海野イルカであった。
「ちょっとぉー!いくら里の中とはいえ、忍者がこんな簡単に背後とられてどーすんのよ?」
はガッチリとイルカの腰に抱きつき、その脇の下からひょっこりと頭を出してイルカを見上げていた。
「そ、そんなこと言ったって・・・!中忍のオレが上忍の気配を察するなんて器用なことが」
できるはずない、と言おうとしたイルカはぴきっと固まってしまっていた。
「イルカちゃーん?」
が不思議そうにイルカを見上げている。
どーして、アナタは気づかないんですか・・・ッ?!(滝汗)
イルカの背を冷たいものが伝っていく。じっとりと冷たい、嫌な汗だ。
「・・・ゴホ。お二人はお知り合いなのですか?」
一気に周囲の気温が下がったような気がした。不機嫌極まりないハヤテの声・・・。
「うんv イルカちゃんとは仲良しなんだ〜♪」
相変わらずイルカに抱きついたままのがにこやかに答えた。
「・・・ほぉ・・・そうなんですか・・・」
「あ、あの、上忍!いい加減、離れてくれませんか・・・?」
「なんで?」
きょとんとした顔の。イルカはめまいがしそうだった。
なんで気がつかないんだ、このヒトは・・・!?
「ひさしぶりに会ったのに、イルカちゃんてば冷た〜い!」
そう言って、いっそうギュッと強く抱きついてくる。
ヒィィィィッ!カ、カンベンしてくれぇっ!!

年下とはいえ、ハヤテは特別上忍である。あたりに漂う殺気じみた雰囲気にイルカはさっさと逃げ出したい気分にかられた。
「あ、あのっ!生徒が待っているんで・・・これで失礼しまーすッ!!」
一瞬ゆるんだの腕からするりと抜け出すと、脱兎のごとくイルカは駆け出した。
「あれー?イルカちゃんってば、どーしたのかな〜?」
「・・・ゴホ」
「ハヤテってば、なんか機嫌悪いの?眉間にシワ寄っちゃってるよ?」
の細い指先がハヤテの眉間に触れた。
「・・・ワザとやってるんですか?」
「なにを?」
ハヤテは深いため息をついた。
――病院の待合室にて。
はこれ以上ないというほどの仏頂面である。それなりに混んでいる待合室で、が帰ってしまわないように、ハヤテはぴったりくっついて座っていた。
「どうしてそんなに病院がキライなのですか?」
「・・・言ったら笑うもん」
むぅとくちびるを尖らせた。ハヤテにはそんな子供っぽいも可愛くてたまらない。
「笑いませんよ、ゴホゴホ」
「てゆーか、あたしよりもハヤテの方が診察してもらった方がいいんじゃないの?」
「私の咳はちゃんと診察していただいていますよ。で?」
「・・・・・・注射」
「は?注射?注射がどうかしましたか?」
「だから、注射がキライなのっ!」
「・・・注射ですか」
ハヤテが笑いをこらえているのがわかったのだろう、はぷぅっとふくれっ面だ。
「笑わないって言ったのに!ハヤテの嘘吐きー!ハヤテなんてキライだもーんっ」
「すみません、つい」
ゴホゴホと咳き込みながら、ハヤテは笑ってしまう。
「さん、さーん!診察室へどうぞ」
「ほら、呼んでますよ」
が立ち上がると、ハヤテも一緒に立ち上がる。
「ちょっと、ハヤテ?もしかして、診察室までくっついてくる気?」
「もちろんです。あなたが逃げないという保障はありませんから。ゴホ」
「・・・ったく」
はヤレヤレと肩をすくめて診察室へ入っていく。その後を追うようにハヤテも診察室へ入った。
「なんじゃ、か。珍しいの、お主が病院にくるとは」
「うるさいなー、ジジィ!」
診察室に居たのは見事な白髭を蓄えた老医師だった。
「さん!院長に失礼ですよっ」
慌ててハヤテが注意するが、はどこ吹く風。老医師――木の葉病院院長はの悪口にも慣れているのか、平気なものだ。
「あたしはねぇっ、このじーさんのお陰で病院ギライになったのよ!」
「・・・ったく。古い話をいつまで覚えておるな、は」
木の葉病院院長を『ジジィ』呼ばわりするに、ハヤテは青ざめた。木の葉病院院長といえばこの里では知らぬ者などいないであろう、名医である。
「いたいけなコドモを騙して、よくそんなことが言えるわね!」
「普通の医者なら『痛くない』って言うじゃろ」
「??」
ひとり会話の見えないハヤテ。そばにいる看護士達には見慣れた光景なのか、くすくす笑っている。
「このじーさんってば、ちびっこのあたしに『注射は痛くないからね〜』なんて言いながら、
すっごく痛い注射を打ったのよ!」
「あれはお前がアカデミーに入る前じゃったろ。いい加減、忘れろ。しつこい女は嫌われるぞ」
「こっちはねぇ、トラウマになってるっての!」
ぷぅっとふくれっつらのだが、老医師は慣れているらしく、さっさと治療を始めた。
「・・・お前なぁ、もっと早く来い!こりゃ相当うまくやらんと傷跡が残るぞ」
「いいわよ、そんなの。別に気にしないもん」
「何言っとる、嫁入り前の娘が。ほれ、そこの花婿殿にも申し訳ないじゃろうが」
「「は、花婿ッ?!」」
老医師の視線の先にいるのは――もちろんハヤテであった。
「な、なに言ってんのよ、ジジィ!ついにボケちゃったの?!」
これにはさすがの院長もムッとした表情を浮かべた。
「失敬な!わしゃ、まだボケとらんぞ」
「じゃ、どこからハヤテが花婿だなんて、そんな妄想を・・・」
妄想・・・あまりといえばあまりなの言葉に、ちょっと傷ついたハヤテであった。
「ほれ、三代目じゃよ。お前も年頃じゃからの」
「全然っ、話が見えないっての!」
次第に苛立ち始めたに、老医師は治療をしながらゆっくりと話し始めた。
「三代目がの、お前もいい年だからそろそろ相手を見つけてやらにゃならん、と言い出してな。
上忍どもと見合いをさせたんじゃよ」
「見合い?あたし、そんなものしてないわよ」
「ここ最近、ツーマンセルばっかり組んでおったろ。誰と組んだ?」
「・・・え?えーと、カカシでしょ、アスマでしょ、それからゲンマ。あとはハヤテかな」
が指を折りつつ応えると、院長はウンウンと頷いた。
「ふむ、皆、木の葉の里の優秀な忍びばかりじゃの。しかも、独身じゃ。
三代目はの、その中の誰かとお前が結婚してくれればと思っておるのじゃよ」
「・・・」
あまりのことに言葉も出ないとハヤテ。
「くの一としては里でも一二を争うお主と、優秀な上忍が結婚して子が生まれれば、
きっとその子も優秀な忍びとなるじゃろう。そうなればこの里も安泰じゃ」
「・・・あんのクソジジィ」
今回の『クソジジィ』はおそらく三代目のことだろう。ハヤテはもはやに注意をする気にはなれなかった。
「病院ギライのお前がハヤテのつきそいで現れたんじゃ、わしが誤解するのもあたり前だ。
ハヤテと結婚する気になったのかと思うたのも仕方ないじゃろ」
「そんなワケないでしょ!」
はすぐさま否定し、ハヤテをがっかりさせたのだった。
意外に病院での治療に時間がかかり、とハヤテが病院を後にする頃にはすでに陽が沈みつつあった。
二人並んで、約束の酒酒家まで歩いていく。
はむっつりと黙ったままである。一方、ハヤテの方も院長の言葉が気にかかり、ずっと黙ったままだった。
あの院長の話は本当なのでしょうか・・・?本当に三代目様が、さんの婿を決めようと・・・?
――なら、さんは誰をえらぶのでしょう・・・?
ハヤテはその事が気になり、普段ならおしゃべりなが黙ったままであることにまで気が回らなかった。
「・・・テ?・・・ハヤテってば!」
「え?」
「どこまで行くつもり?」
ハッと気がつくと、ハヤテは酒酒家を通り過ぎようとしていた。
が不思議そうにこちらを見ている。
「どうしたの、ハヤテ?」
「あ、いいえ・・・。なんでもありませんよ。ゴホ」
「そう?じゃ、入ろうよ。みんな、もう飲んでるみたいよ」
そういわれれば、いつものメンバーの楽しげな笑い声が聞こえる。
正直なところ、あまり飲みたい気分ではなかったが、自分の知らないところでを他の男たちと一緒にはさせたくなかった。
「ええ、そうですね」
ハヤテは渋々、暖簾をくぐった。
いつもの座敷に、いつものメンバーが揃っていた。
カカシにアスマ、そしてゲンマにアンコ、木の葉の上忍・特別上忍御一行様といった感じである。
「あ、ー!」
「あら、アンコも来てたんだ」
アンコはすでにできあがっているらしく、かなりの上機嫌である。
「もちろんよー!こんな面白いモノ、見逃す手はないわよ〜」
「面白いモノって、なぁに?」
アンコは、きょとんとしたの背中をバンバン叩いた
「いいの、いいの、こっちのこと!ほら、、なに飲むの〜?」
「えーと、とりあえずビールかな。ハヤテは?」
「私も同じものを」
皆が楽しそうに騒ぎながらグラスを重ねている中、ハヤテはひとり静かにグラスを傾けていた。
それ自体はもともと珍しい光景ではない。
ハヤテは酔って騒ぐタイプではなかったが、皆が騒いでいる中にいるのは嫌いではない。
しかし、今夜は少し違っていた。
ハヤテの隣にはアンコ、その隣にカカシ。向かい側にはアスマとゲンマに挟まれて座る、の姿があった。
座敷のテーブルは大きく、テーブルを挟んだとはすこし距離がある。しかも隣ではアンコが騒いでいるので、とアスマ、ゲンマが何を話しているのか、聞きづらい状況であった。
それでも楽しげなの表情は充分見てとれ、ハヤテの苛立ちは募っていった。
おまけに、脳裏には院長の言った『見合い話』のことが浮かんでくる。
院長の言った見合い相手に両脇を固められ、楽しげに笑っている・・・。
――さんはどちらかを選ぶつもりなのでしょうか・・・?
今はアスマとゲンマと楽しげに話しているだが、この場にはもう一人カカシがいる。
この三人のなかで一番と親しいのは、幼馴染でもあるカカシだろう。
カカシも静かにグラスを重ねていたが、時折と目が合うとにこやかに微笑んでみせる。
それに大しても優しげな微笑で返している。まるで、恋人同士のように・・・。
ハヤテの中で、ジリジリと嫉妬心が頭をもたげてくる。それを誤魔化すかのように、ハヤテは次々とグラスを空けていった。
「どしたの、ハヤテ?なんか今日、ペース速いじゃん」
「アンコさんに言われたくありませんよ、ゴホ」
とはいえ、普段の酒量をかなり超えていた。普段のハヤテは酒を過ごすことはなかった。
無意識のうちに自制してしまうのだろうか、ハヤテは何事に対しても夢中になりすぎる
ということはなかった。酒もあくまで楽しいと思える範囲でしか飲まない。翌日に任務がある場合はもちろん、休みであっても飲みすぎることはなく、二日酔いなどには絶対にならない。
しかし、今夜はかなりのハイペースであった。いつもなら「飲め飲め」と半ば強制するアンコがためらうほどに・・・。
「ちょっと、アンタ、大丈夫なの?」
「大丈夫ですよ」
いつもは血色の悪いハヤテの頬が少し赤い。酒に強いのか、酒量をセーブしているせいなのか、酔って赤くなったことのないハヤテがである。
ハヤテは焼酎のロックを一息に飲み干した。
「ちょ・・・ハヤテ?!」
「大丈夫です、ゴホ」
目の前では相変わらず、が楽しげにしゃべっている。かと思うと、ゲンマの腕がの肩にまわされ、グイと引かれたがゲンマの胸に倒れこむ。
「もうヤダ、ゲンマってばー!」
「いいだろ、?いい加減、オレと付き合ってくれよ」
の楽しげな笑い声が響く。その腕の中から逃れようともせず、楽しげなの様子にハヤテの苛立ちはなおいっそう募っていく。
「・・・ちょっと失礼しますね、ゴホ」
これ以上この場に居たら、ゲンマの腕の中からを攫ってしまいそうになる。
そう思ったハヤテは、皆に断り、酔いを醒ますためにひとり店の外にでた。
「・・・」
ハヤテは深いため息をついた。
薄暗い路地から見上げた夜空には美しく星が瞬いている。
外の冷たい空気を吸ったおかげか、ほんの少しイライラがおさまったような気がした。
「・・・約束をしたわけでもないのに」
そう呟いて、ハヤテは自嘲的な笑みを浮かべた。
に想いを告げたわけでもない。ましてや、なにかを誓い合った仲でもない。
それなのに、他の男と楽しげなをみていると、嫉妬の炎に焼かれてしまいそうになる。
からすれば、自分はただの後輩。良くて弟のような存在だ。
どちらも恋愛の対象ではない・・・。
「どうしたら私は・・・」
「――ハヤテ?」
「!」
そこには、心配げな様子のが立っていた。
「ハヤテ、大丈夫?気分でも悪いの?」
「・・・私なら大丈夫です。皆さんのところへ戻ってください」
今はに会いたくなかった。しかも二人きりでは。
「でも・・・」
「ほうっておいてください!」
常になく、声を荒げたハヤテにが驚いた表情をしていた。
「ハヤテってば、どうしたの?なにかあった?」
まるで子供に質問するような口調のに、ハヤテの苛立ちはピークに達していた。
「ほうっておいてください、と言っているでしょう!」
珍しくきつい口調のハヤテに、はビクリと震えた。
「・・・わかった。ゴメンね」
ポツリと小さな声では答えると、くるりと踵を返した。
すこしうなだれたように見えるの背中に、ハヤテの心がチクリと痛んだ。
は自分を心配して、わざわざ席を抜けてきてくれたのだ。
それが嬉しい反面、自分ではなく他の誰に対しても、は同じ行動をとることが容易にわかっていたハヤテは複雑な気持ちだった。
「――待ってください」
「え?」
呼び止められたがパッと振り返った。
「・・・あなたは、誰を選ぶのですか?」
「え?何のこと?」
「昼間の院長のお話ですよ」
「ああ、アレね・・・」
一瞬困ったような表情を浮かべたは、頭をポリポリと掻いた。
「・・・ハヤテには関係ないよ」
ぽつりと呟かれたの言葉に、ハヤテは自分の中で何かが壊れたような気がした。
「どうして・・・あなたは・・・っ?!」
「ハヤテ?」
華奢なの腕をグイとつかむと、胸の中へ抱き寄せる。激情にかられてこんな行動に出たはずなのに、どこか冷静な自分も居て。
こんな表情をさせたいわけではなかったのに・・・。
いくら上忍とはいえ、男女の力の差は歴然で。の瞳には微かにだが恐怖心が宿っている。
それがまたハヤテを苛立たせる。
「ちょ・・・どうしたのよ、ハヤテってば?」
「私は・・・!」
胸のうちではさまざまな感情が渦巻いていて、うまく言葉にできない。
「離してっ」
離せるわけなどなかった。
を愛しく想う気持ちと、受け入れてもらえない悔しさが相まって、ハヤテはいっそう強くを抱きしめた。
『関係ない』などと言われるのならば、いっそのこと『嫌いだ』といわれた方がマシだ。
このままこの腕をほどいたとしても、以前のような二人には戻れないことはよくわかっていた。
それくらいなら、いっそ・・・
「・・・んんっ・・・!?」
初めて触れたのくちびるは柔らかく甘く、ハヤテを魅了する。
自分の想いを無視されるよりは、に厭われたとしてもなにか証を残したかった。
腕の中で逃れようと暴れるをさらに強く抱きしめ、そのくちびるを貪る。
「・・・クッ!」
ポタリ、とハヤテのくちびるから血が滴った。が噛みついたのだ。一瞬緩んだ腕のあいだからするりとは抜け出した。
「・・・ハヤテなんか大っきらい!」
の瞳から涙が溢れていた。ハヤテはハッと胸をつかれた。
これまで何度も任務を共にし、プライベートでも友人として長い時間を過ごしてきた。しかし、が涙を流すところなど、一度も見たことが無かった。
「さんっ!」
の姿は薄暗い路地の奥に消えた。
くちびるに滲んだ血をぬぐう。我ながら愚かなことをしたものだと思う。
けれど、こうせずにはいられなかったことも事実で・・・。
もう二度と、あの優しい声で『ハヤテ』と自分の名を呼んでくれることがないのかと思うと、どうしようもない寂寥感に襲われる。
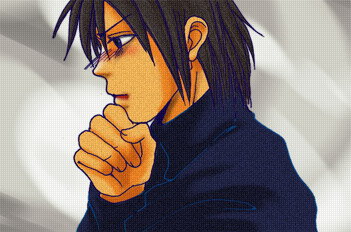
ハヤテは闇のなか、ひとり立ち尽くしていた。
すっかり陽は暮れて、夜空には美しい三日月が輝いている。
ハヤテはの姿を探して、里内を歩いていた。を見つけたとして、なんと声をかければいいのかわからなかったのだが・・・。探さずにはいられないハヤテであった。
昨夜、あの後店には戻ってこなかったのだ。
翌日、朝からあちこち探してみたのだがを見つけることは出来ず、夕刻になってハヤテは酒酒家の近くまでやってきていた。
「なら来なーいよ」
「・・・カカシさん」
路地の奥から声をかけてきたのはカカシだった。片手をポケットに突っ込み、すこし猫背気味の相変わらずの立ち姿だ。
「オマエ、にキスしたんだってー?それもムリヤリ」
「っ?!」
カカシの言葉に、頬に血が昇る。
「なんでオレが知ってるのかって?、泣きそうな顔でオレのとこへ来たんだよ。
『あたし、ハヤテに嫌われちゃった』って言ってさ」
「・・・どこをどうしたらそんな誤解を・・・」
「に腹を立てて、嫌がらせにキスしたと思ってるみたいだねぇ、は」
「嫌がらせ・・・」
ガックリと膝の力が抜けそうなハヤテであった・・・。
「はそう思ってるみたいだったから、オレも『ハヤテは意地悪だから、近づかないほーがイイよ』って
言っといたv」
「なっ!?なんでそんなコトを・・・!?」
「はヘンに子供みたいなとこがあるから、素直にウンって頷いてくれたよ」
「・・・意地悪なのは、あなたの方でしょう。ゴホ」
「さぁ、それはどうかな〜?」
心底楽しそうにカカシは笑った。一方、ハヤテはというと、苦虫を噛み潰したような表情である。
楽しそうに笑っていたカカシだったが、ふっと真顔になった。
「なぁ、ハヤテ」
「ハイ?」
「・・・本気じゃないなら、には近づくな」
「あなたには関係ないでしょう、カカシさん」
カカシとハヤテ、二人の間の空気がピンと張り詰めた。
「確かにオレには何も言う権利はないさ。けどのことは大切に思ってるよ、幼馴染だしね」
「・・・」
「中途半端な気持ちはを傷つけるだけだ。オレはを悲しい目にはあわせたくない」
「・・・私はあきらめるつもりはありません」
そう言い残すと、ハヤテの姿はふっと掻き消えた。
「・・・ったく、世話の焼ける二人だねぇ」
ククッと、カカシは楽しそうな笑みをもらした。
「娘を嫁に出す父親の気持ちってのは、こんなもんなのかねぇ〜?」

クスリと笑って、カカシは夜空に輝く月を見上げた。
その頃、はひとりで森の奥深くへと分け入っていた。大木の梢に腰掛けて、足をぶらぶらと揺らしながら月を眺めている。
――昨日出会ったカカシの言葉が頭の中で響いていた。
『もっと素直になればいい』
ハヤテから逃げ出したあと、は偶然にも飲み会帰りのカカシと出会ってしまったのだ。
涙はきれいに拭ったつもりだったが、カカシには隠し通すことができず、ことの顛末を話すしかなかった。
「で、なんでオマエは泣いてるの?」
「それは・・・」
はうつむいたまま、答えられなかった。
「ハヤテのことが好きなんだろう?」
「・・・!?」
うつむいたままのの頭を、カカシはポンポンと叩いた。
「いいんだよ、オレには隠さなくても。オマエのことは、オレが一番よく知ってるんだから」
「・・・かなわないなぁ、カカシには」
恥ずかしそうなを見て、カカシはクスクス笑った。
「何年つきあってると思ってんの?全部お見通しだよ〜んv」
「もう・・・っ!からかわないでよ」
照れ隠しなのか、はカカシの背中をバンバン叩いた。
「素直に『好き』って言えばイイのに〜」
「だって・・・」
もごもごと、珍しく歯切れの悪いである。
「『だって』、ナニ?」
「だって、あたし・・・ハヤテより年上だし、全然女らしくないしっ!
ハヤテは、年下の可愛い女のコとかの方が好きそうだし!
振られて気まずくなったりしたくないんだもんっ」
一気にまくしたてたに、カカシは口布の下で笑いをこらえるのに必死だった。
昔っから、鈍い鈍いとは思ってたけど、ここまでとはねぇ・・・。
ハヤテも苦労するな・・・。ま、それも面白いけどv
「ま、オレからのアドバイスとしては『素直になれ』ってコトかな〜。
ハヤテに振られたら、オレと付き合おうっかv」
「もう、カカシってば・・・」
カカシは、幼馴染のが可愛くて仕方なかった。男女のそれとは違う、例えて言うなら兄妹のような関係だろうか。
自分でもシスコン(?)かと思うが、が悲しむような目にあわせたくはない。
ちょっとハヤテに釘でも刺しておくか、と思ったカカシであった。
「ま、よく考えなさい。時間はたっぷりあるんだから」
「うん・・・ありがと、カカシ」
そう言うと、カカシはヒラヒラと手を振って行ってしまった。
一人残されたは、ぼんやりと月を見上げた。
柔らかな月の光はある男のことを思い出させる・・・。忍らしからぬ風貌と穏やかな雰囲気の年下の男を意識したのはいつだっただろう?
初めてチームを組んだ時、正直足手まといにならなければいいがと思っていた。
しかし、彼は冷静な判断でもって仲間の危機を救った。そして、は初めて『三日月の舞』を見たのだ・・・。
背筋がゾクリとするほど、華麗で美しい技だった。その美しさに、は魅了された。
は月を見上げ、小さくため息をついた・・・。
ハヤテがようやくを見つけたとき、月は中天にかかっていた。
は大木の切り株に腰掛けて、ぼんやりと月を見上げていた。
「・・・さん」
「ハヤテ」
ゴホと軽く咳払いをしたものの、ハヤテはに何と言ってよいのかわからず、言葉に詰まった。
「ゴメンね、ハヤテ・・・」
「え?」
「今までゴメン」
そう言うと、どこかすっきりしたような顔では微笑んだ。
「ついハヤテに構いたくなっちゃって、ね。ハヤテはいつも優しいから、うっかりしちゃって・・・。
ハヤテだって、機嫌の悪いときだってあるよね。
それなのに、うるさく構いにいっちゃってゴメンね」
「さん・・・」
「――ハヤテにも怪我させちゃったね」
「これは・・・」
一瞬カッと頬が熱くなる。ハヤテが手をやるよりも早く、ほんの少し腫れたくちびるにの指先がそっと触れた。
柔らかな指先から、ふわりと温かなチャクラがゆっくりと流れ込んでくる。
「これで塞がったかな〜?」
傷跡を確かめるかのように、の指先がくちびるをなぞっていく。
「・・・?!」
トクン、と鼓動が一拍早くなったような気がした。
「さんっ!」
「へ?」
ハヤテはたまらなくなって、口元に添えられていたの手を取った。
「ハヤテ?」
「謝らなければならないのは、私のほうです」
は不思議そうにハヤテを見上げた。
「私は嫉妬していたんです・・・」
「嫉妬・・・?」
「アスマさんやゲンマさんと仲良く話しているのをみて、嫉妬してしまったのです。
あなたは誰にでも優しい――その優しさが、私にだけ向けられたのならと・・・」
「ハヤテ・・・」
「あなたを独り占めしたかった・・・。けれど、そんなことが叶うわけもなくて・・・。
それが悔しくて、あなたの意思を無視して、あんな事をしてしまいました」
「・・・」
「本当は一番にあなたに伝えなければいけない言葉があったのに・・・。
――私はあなたが好きです」
「・・・?!」
いつも冷静沈着なの驚いた顔など、これまでハヤテは見たことがなかった。
自分の言葉がこんなにもを動揺させたのかと思うと、こんな状況だというのになぜだかおかしくなって、ハヤテは口の端に笑みを浮かべた。
「あなたにとって、私は単なる後輩に過ぎない・・・。そのことはよくわかっているつもりです。
ですが、私は・・・」
手に入れられないことが悔しくて、無理やりにくちづけてしまった。
それでも諦めの悪い自分が居て。愚かだとわかっているのに、この想いを止められない。
「・・・ウソでしょ・・・」
かぁぁとの顔が真っ赤になっていく。
「ハ?」
「か、からかわないでよねっ!ハヤテが、あたしのことなんか好きなワケないじゃない!」
「あ、あのさん?(汗)」
「だってあたし、ハヤテより年上だし、全然可愛くないしっ!
女らしくもないし、どっちかっていうとガサツだもんっ!
ハヤテの好みのタイプじゃないしっ」
真っ赤になりながら一気にまくし立てるに驚いたハヤテだったが、ゴホと軽く咳き込んで、クスリと笑みを浮かべた。

「あなたは充分可愛いですよ」
「・・・っ!?」
恥ずかしさのあまりか、こちらに背を向けてしまったに、ハヤテはそっと手を伸ばした。
「・・・さん」
そっと後ろから抱きしめ、その耳元で甘い声でささやく。
「――もう一度、最初からやり直させてください。
私はあなたが好きです」
「・・・・・・あたしも・・・」
ポツリ、とハヤテにしか聞こえないような小さな声が聞こえた。ハヤテは思い切りを抱きしめた。
蒼い月光の中、二つの影はひとつに重なり、しばらく離れることがなかった。
――翌日、人生色々にて。
「オイ、!おととい、俺たちを残して、勝手に帰りやがって!」
「あ、ゴメン(汗)」
が人生色々に入っていくと、そこにはおととい飲みに行ったメンバーが偶然にも勢ぞろいしていた。
「オイ、?ハヤテとなんかあったのか?え?」
不機嫌そうなゲンマがにじり寄ってくる。そして今度は、煙草をイライラとふかしているアスマ・・・。
「二人して戻ってこねぇしよ。ああ?」
思わず、後ずさってしまった・・・。
「いや、あの・・・」
「まさかハヤテと・・・?」
「どうなんだよ、?!」
二人に詰め寄られ、たじたじの。そんなを、アンコと紅はにやにやと笑いながら見ていた。
「あの、そのっ、あたしとハヤテはそんなんじゃ」
「『ない』とでも言うつもりですか?ゴホ」
「ひゃっ?!」
突然背後からぬぅっと手が伸びてきたかと思うと、の細い腰にまきつき、グイと抱き寄せられた。
「きゃ、ハヤテ?!」
「・・・往生際の悪い方ですね。いい加減素直になってくださいよ、ゴホ」
の耳元でこっそりと囁く。途端にの頬が赤くなり、それを見ていたゲンマとアスマは顔を見合わせた。
「ゲッ!とハヤテって、つきあってんのか?!」
「いや、その・・・つきあってるっていうか・・・」
「ええ、そうなんです。ゴホ」
と、最高ににこやかなハヤテ。さりげなくの口元を手で覆い、がしゃべれないようにする。
「もう、あんなコトやこーんなコトもしてしまいましたので、さんには手を出さないでくださいね」
「・・・ふがふが!(なに言ってんのよ!?)」
「そういうワケですので、よろしくお願いしますね。ゴホ」
呆気に取られている皆の前から、ハヤテはを瞬身の術で連れ出したのであった。
半ば攫うようにしてハヤテにを連れ去られ、あとに残された木の葉の面々はというと・・・。
「ハヤテってば怖えーっ!」と、ゲンマ。
「全然、目が笑ってなかったな」と、アスマ。
「――二人とも、ちゃっかりハヤテにを持っていかれてるじゃん」
ポツリとつぶやかれた、アンコの鋭いツッコミに二人は一瞬言葉に詰まった。
「恋ってのはな、ライバルがいる方が燃えるんだよっ」
「あんなヒヨッコにを渡せるかってんだ」
「・・・(カンペキ横恋慕だと思うけど)」
アンコは、これからの退屈しない日々を思い、ニヤリと笑みを浮かべた。
一方、優雅にコーヒーを楽しみつつ、事態を見守っていた紅とカカシの方は・・・。
「ねぇ、カカシ?いいの、あれで?」
「なにがー?」
「なにがって・・・ハヤテとに決まってるでしょ」
「――いいさ、が幸せなら、な」
「カカシ・・・」
穏やかな笑みを浮かべたカカシに、紅は何も言うことができなかった。
「でもまぁ、を泣かせるようなことがあったら、タダじゃおかないけどねーv」
「・・・(やっぱシスコンだわ)」
ハヤテの受難の日々・・・いや、幸せな日々は始まったばかりのようである。
【あとがき】
『9999hitリクエスト』碧さまのリクエストでございます。
リクエストといいますか、碧さまからコラボのご提案をいただき、こんなに素敵なイラストを
たくさん描いていただいちゃいましたー!
某所に掲示板をお借りして、打ち合わせを始めさせていただいたのが5月(うわ・・・)
しかも、ストーリーはほとんどわたしが勝手に書き散らかし、碧さんには申し訳もなく・・・(汗)
こんなハヤテさんでごめんなさーい!
お話にあわせてイラストを描いていただけるというのは、非常に貴重な体験でした!
このページを作っているときも「なんて贅沢〜♪」とルンルン気分v
碧さま、リクエスト&素敵なイラスト、ほんとにありがとうございましたー!!
最後まで読んでいただいてありがとうございました。
2004年10月23日